

1982年に創刊された女性ファッション雑誌『CanCam』。
現在は雑誌を主幹にWebメディア「CanCam.jp」も運営し、雑誌は加藤真実編集長、CanCam.jpは渡邉恒一郎編集長がそれぞれ担当している。
読者によるファンクラブ組織「CanCam Friends」は現在1万1000人の会員を抱え、編集部は日々、読者との交流や情報収集をコンテンツ制作。
今回はそんなお二人に、CanCamが橋渡し役となる地方創生の可能性と、具体的なアイデアについて話を聞いた。
『CanCam』では、インフルエンサーや読者モデルによるチーム「CanCam it girl」を結成。現在は約50人が在籍し、地方在住の人も多い。彼女たちと対話すると、いまの20代女性の“東京観”や価値観に変化が見えてくるという。
渡邉編集長(以下、渡邉):「地方在住のit girlメンバーと話すと、“東京=遊びに行く場所”という認識はありますが、以前のように“いつか住みたい憧れの街”という感覚はあまりないように感じます。InstagramやYouTubeを通じて、地方にいながら自己表現も仕事もできる。だから『就職は地元でいいかな』と考える人も多いですね」
加藤編集長(以下、加藤):「むしろ、自分に合った環境を大事にする“地に足のついた価値観”を持っている印象がありますね。よく“若者の結婚離れ”が話題になりますが、CanCam読者にアンケートを取ると、半数以上が『将来は結婚したい』と回答しています。都会か地方かにこだわらず、“住みやすい場所で、信頼できる人と家庭を築きたい”というライフビジョンを持っている人が多いですね」

渡邉「だからこそ、彼女たちは情報にもとても敏感です。“こう生きたい”という軸をもとに、自分で選び取る力がある。私たちもそうした価値観に応えられるコンテンツをつくっていかなければと考えています。たとえば、地方移住についてのリアルな声を紹介した記事もCanCam.jpで反響がありました。実際に移住やUターンに興味を持っている人も少なくありません」
都会の人は冷たいって本当?20代女子に聞く「地方移住」と「上京」のリアル
加藤「“かわいい服”や“人気アイテム”はSNSでも見られますが、今の読者が本当に惹かれるのは、“誰がどんな思いで作ったのか”という背景にあるストーリーなんです。
そして彼女たちは、お金の使い方にも非常にメリハリがあります。流行を一通り買うのではなく、“自分が本当に好きなもの”“自分に合っていると思えるもの”には迷わず投資するけれど、それ以外には使わない。とてもスマートな消費感覚を持っています」
渡邉「そうした“自分の価値観で選び抜いたもの”への投資意識は、推し活にも通じています。たとえば、好きなアーティストやキャラクターの“聖地巡礼”やイベント参加のために、遠方まで足を運ぶCanCam読者もたくさんいます。推し活をきっかけに地方を訪れる──そうした行動が、いまや地域活性の一端を担っているとも言えるんです。CanCamとしても、この領域には強い関心を持っています」
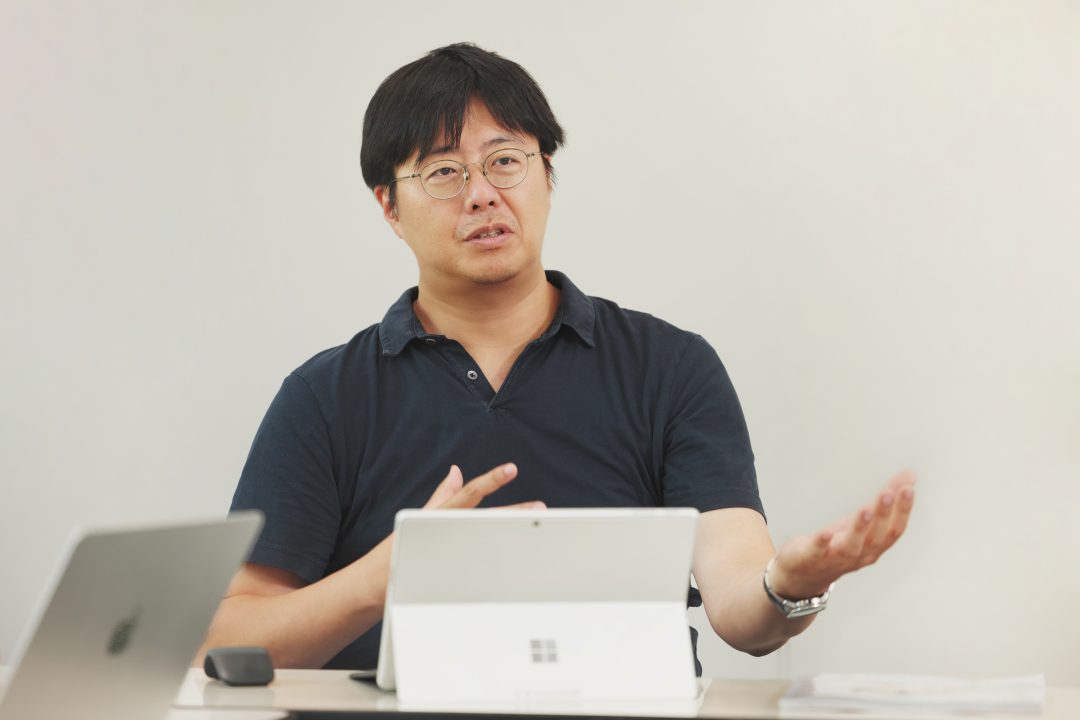
読者の価値観をヒントに、CanCamでも地方と若い世代をつなぐという視点から新しい可能性について考え始めている。
渡邊「たとえば“友達をつくる旅”のような企画をCanCam主催で実施できたら面白いと思っています。今の20歳前後は、ちょうどコロナ禍で高校や大学生活を過ごした世代で、リアルな人間関係を築く機会が少なかった。だから、撮影やイベントで同世代が集まると、『お友達になりましょう!』と連絡先を交換できるのがすごく嬉しいそうです。地域を超えて人とつながる体験ができる旅があれば、CanCamならではの“新しい旅の価値”を生み出せるのではと思っています」
加藤「もうひとつ、CanCam読者が“行ってみたくなる理由”として大きいのが、“その土地にしかないモノやストーリー”。
たとえば“ご当地コスメ”や“その場所でしか手に入らないおみやげ”には、感度の高い女性たちのアンテナがすぐ反応します。最近では“#自然界隈”というハッシュタグが人気になったり、“自然の中で癒される非日常”を求めて奥多摩など都内近郊のローカルエリアに足を運ぶ人も増えています。そうした気持ちに寄り添いながら、地域の魅力を“今っぽく”編集して伝えるのが、CanCamの得意分野だと考えています」
取材・文/高山 惠 撮影/黒石あみ(小学館写真室)